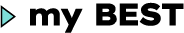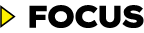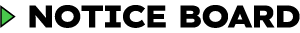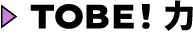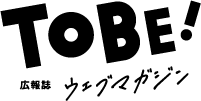
2025年3月
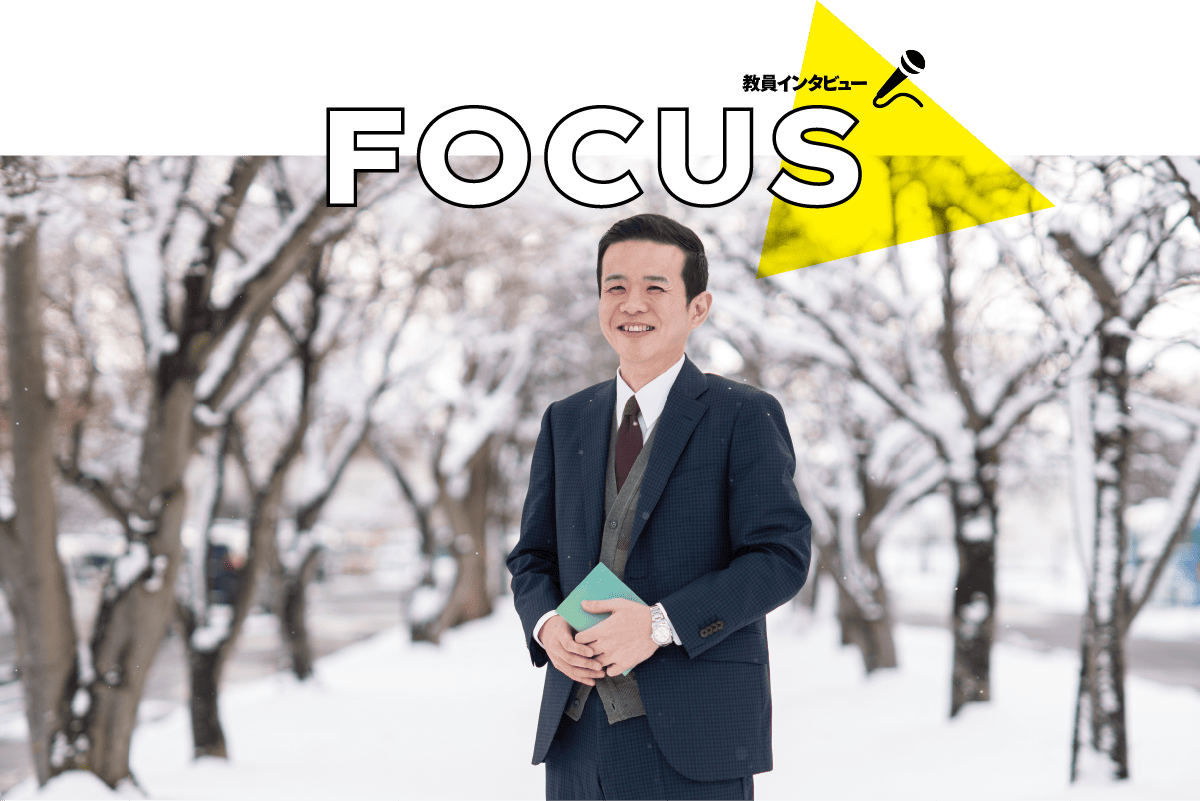
“子どもを教える”ことは“子どもから学ぶ”ということ


先生が指導されている「特別支援教育」とはどのようなものですか。
特別支援教育は子ども一人ひとりの特性を踏まえて、そのニーズに応じた支援を行う教育です。視覚・聴覚・発達障害の子どもや外国ルーツの子ども、貧困や虐待などの問題で困難な家庭にある子どもも特別な支援を必要とする子どもとして対応が求められます。特別支援教育の基礎になる考え方に“障害は環境によってつくられる”という言葉があります。子どもの医学的な障害に加えて、注目すべきは彼らを取り巻く環境。教室や保育室の様子、先生や友達、家庭、地域…それらの環境次第でその子の生活の質が大きく異なってくるわけです。そして、もう一つ重要なことは「個性」と「特性」の違い。学校では「いろんな個性の友達と仲良く」とよく言われますが、30人が同じ教室にいても暑がる子もいれば寒がる子もいるように、それぞれに生まれ持った特性があり、そこに配慮できなければその子の学びや生活の質は変わりません。個性を尊重することは大事ですが、同時にその特性もしっかりと理解する必要があります。



授業をする上で大切にしていることは?
“子どもを教える、保育する”ことは、同時に“子どもから学ぶ”ということ。このことについて学生に意識してもらえるように話しています。子どもに教える立場ではあるけれども、子どもに対してままならないとき、自らに問題はなかったかと謙虚に振り返る姿勢を持ってほしいです。何らかの課題を抱えている子どもについて考えるときには、学生には他人ごとではなくて、現在の自分にももしかすると特別なニーズがあるのではないかという視点で考え、自分ごと・自分たちごとにしてほしいですね。授業ではICTを活用。授業内容のスライドが学生の手元のスマートフォンやパソコンに反映されるシステムで、学生から匿名で意見や質問も送れます。手を挙げられないけれども意外と意見を言いたい学生も多いです。安心安全な環境でこそ、参加したいという前向きな気持ちや、興味関心が育つというのは、子どもも大学生も同じ。そのように考え、授業内容や形式を日々模索しています。

わかり合いたいと思い続けることで相手に一歩近づける


学生へメッセージをお願いします。
“人はわかり合えない、けれど信じ合うことができる”ということです。例えば都会育ちの人と田舎育ちの人が「夕焼け空って切ないよね」と話が合う。しかし、都会の夕日はビルとビルの間に沈んでいく夕日かもしれないし、田舎の夕日は山間に沈んでいく夕日かもしれない。話は合っているけれど、都会っ子と田舎っ子はある意味わかり合っていない。他人の見ている世界、そのすべてを理解することは不可能ですが、お互いを信頼することはできます。そのためには、相手と愚直に場と時間の共有を重ねるしかありません。それで完全にわかり合えなくてもその人の見ている世界に一歩また一歩と近づくことができるので、学生の皆さんにはわかり合えないけれどもわかりたいと思う気持ちをいつも持ち続けてほしいです。


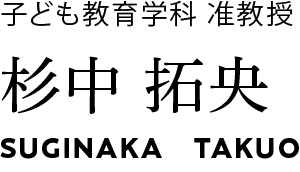
東北文教大学 人間科学部 子ども教育学科 准教授・学長補佐。博士(障害科学)。日本学術振興会特別研究員、早稲田大学人間科学学術院助手、小田原短期大学保育学科専任講師を経て2022年東北文教大学人間科学部に着任。専門分野は特別支援教育。東京都、福島県、山形県で保育士等キャリアアップ研修の講師も務める。