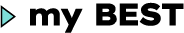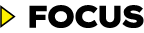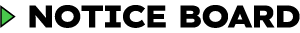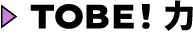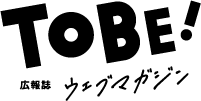
2025年9月
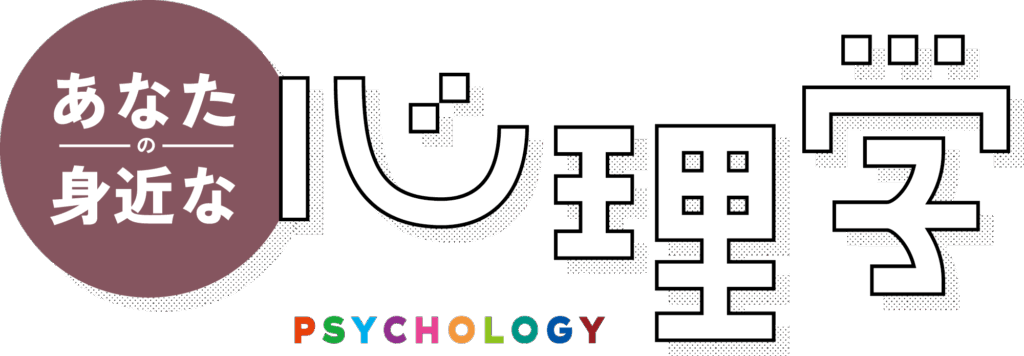
「心理学は特別な人のもの」—— そんなイメージを持っていませんか?
実は、日々の暮らしの中にこそ、心理学の視点が役立つ場面がたくさんあります。
今回は心理学を専門とする先生にお話を伺いながら、心の動きや思考のパターンなど、身近なテーマを通して心理学の面白さをひもといていきます。
よいこと、悪いことは、
いつから芽生える?
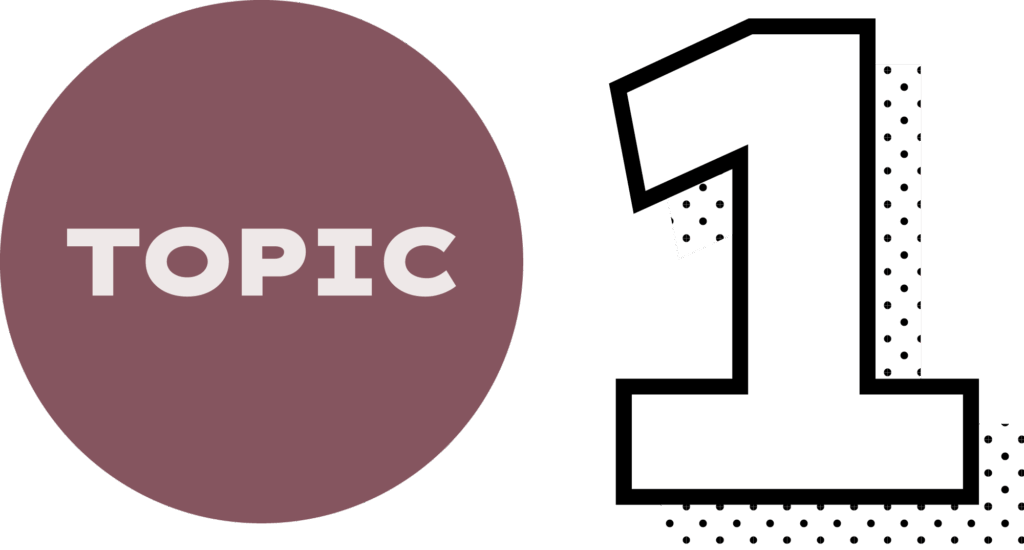
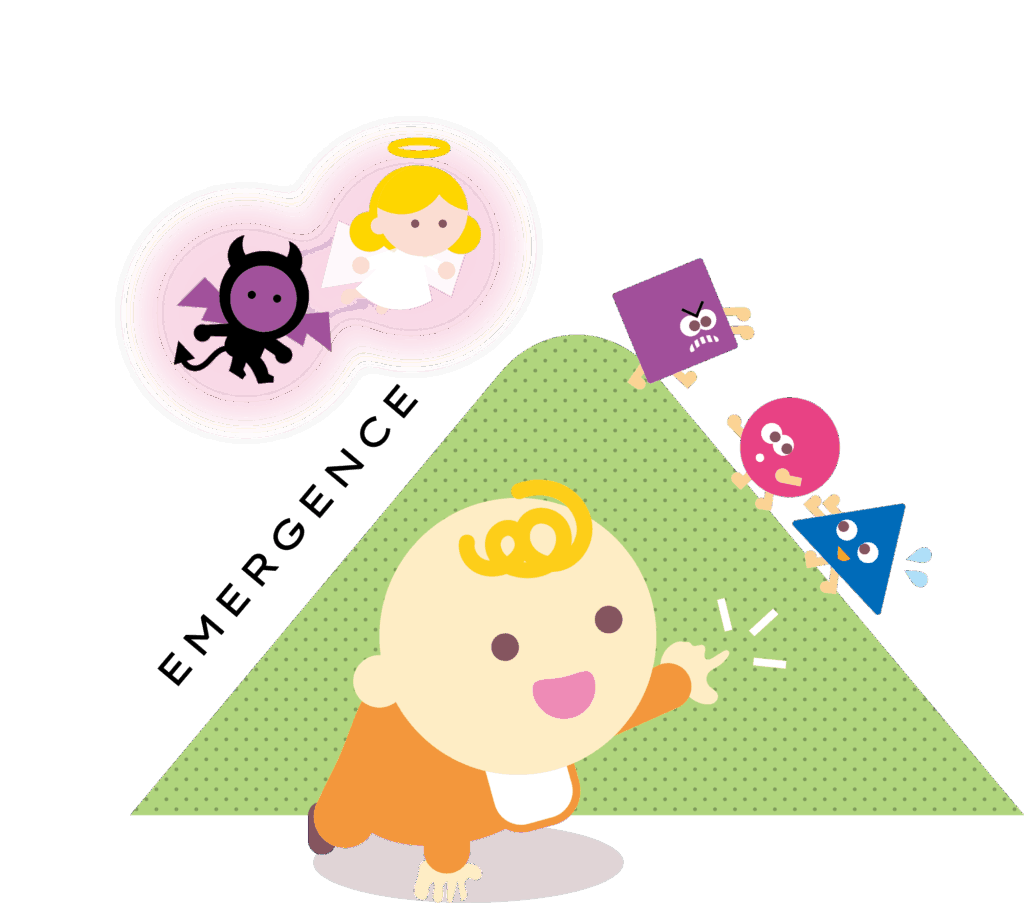
ある実験で、生後6カ月の赤ちゃんに坂を上ろうとする丸い図形を見せた後、その動きを助ける三角形と、邪魔をする四角形の映像を見せました。最後に三角形と四角形を並べて赤ちゃんに選ばせると、赤ちゃんは「助けた」図形に手を伸ばしました。図形の配置を変えても結果は同じ。子どもは興味のあるものや好きなものを手に取ろうとするものなので、助けてくれる良い人の方を選ぶという、善悪の基本がすでにこの時期から芽生えているのです。
夢中になるって、何だろう?
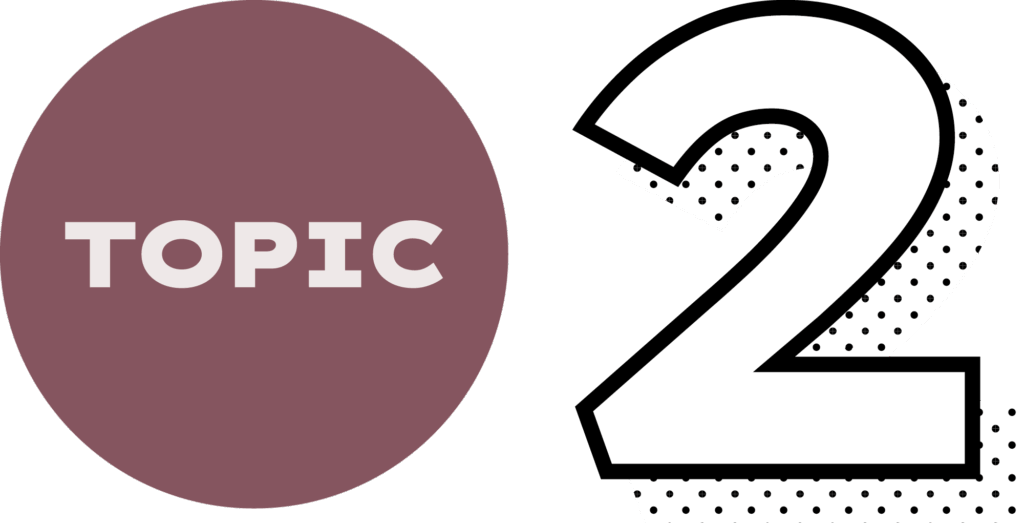
何かに夢中になり、時間も自分の存在も忘れるような集中状態―それは心理学で「フロー体験」と呼ばれます。スポーツでは「ゾーン」、ダンスでは「トランス」とも言われ、極度の集中がパフォーマンスを最大限に引き出します。フロー状態に入るには、明確な目標、すぐに返ってくるフィードバック、そして自分の能力よりほんの少し高い課題(普段の力の4%くらい上)に挑戦することが鍵です。これは勉強にも応用できます。「やる気が出ない」と感じるときこそ、少しだけ難しい問題に取り組んでみる。すると「やってみよう」という気持ちが芽生え、さらに答えが返ってくることで夢中になって取り組める。日常の中の “ちょっと上の挑戦”が、私たちをフローへと導いてくれるかもしれません。
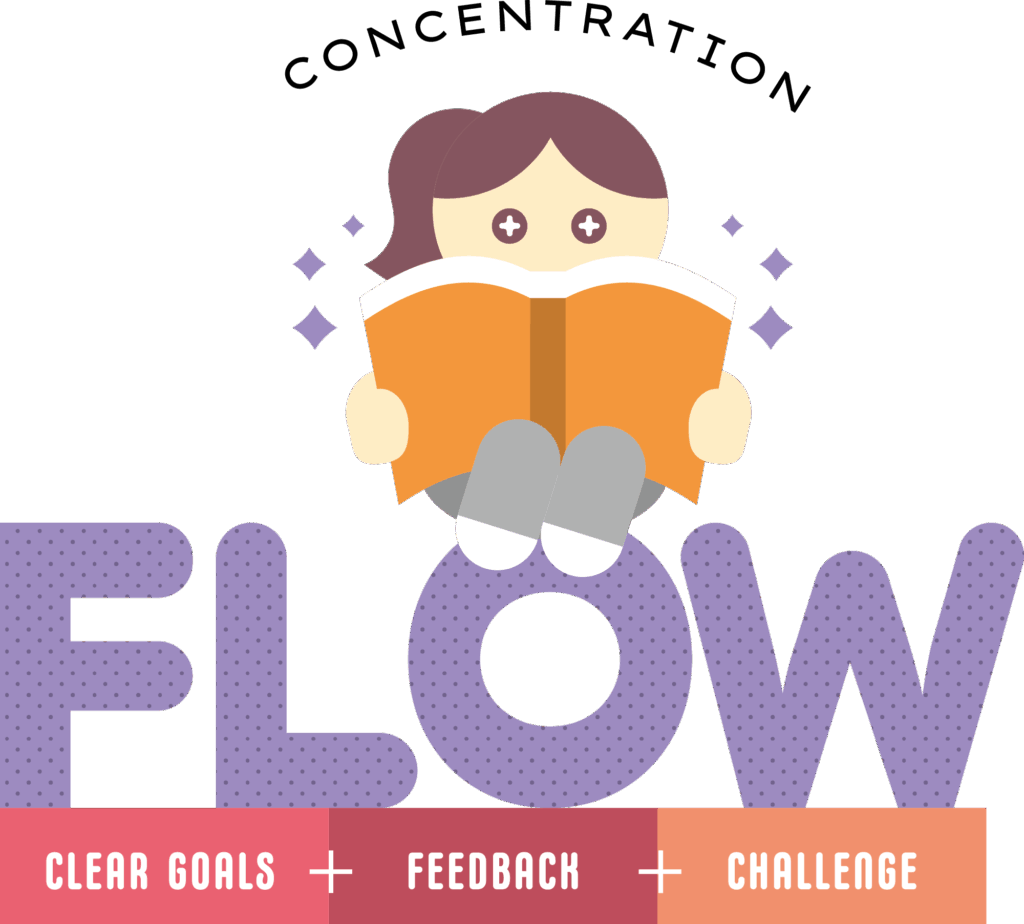
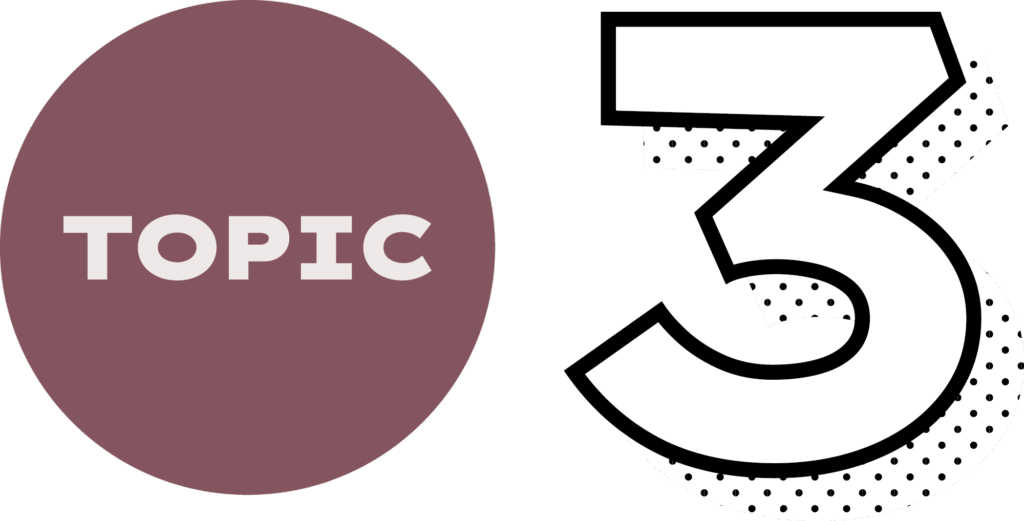
強い自信と、弱い自信
無気力の強い子どもたちに算数の課題を解いてもらうという実験を行いました。一方のグループは簡単な問題で成功のみを経験。残りのグループは成功も失敗も経験し、失敗の際に「努力が足りなかった」と考えるように訓練されました。すると、成功体験のみのグループは確認テストで失敗すると再び無気力に。 反対に、成功も失敗も経験したグループは失敗してもやる気が持続されました。 安易な成功は実は「弱い自信」にしかなりません。成功も失敗もある中で、失敗したときに努力不足だったから次に挑戦しようという気持ちが「強い自信」を育てます。「自分にはできる(だろう)!」と信じることができれば強い自信につながり、めげずに挑戦し続ける力になっていきます。
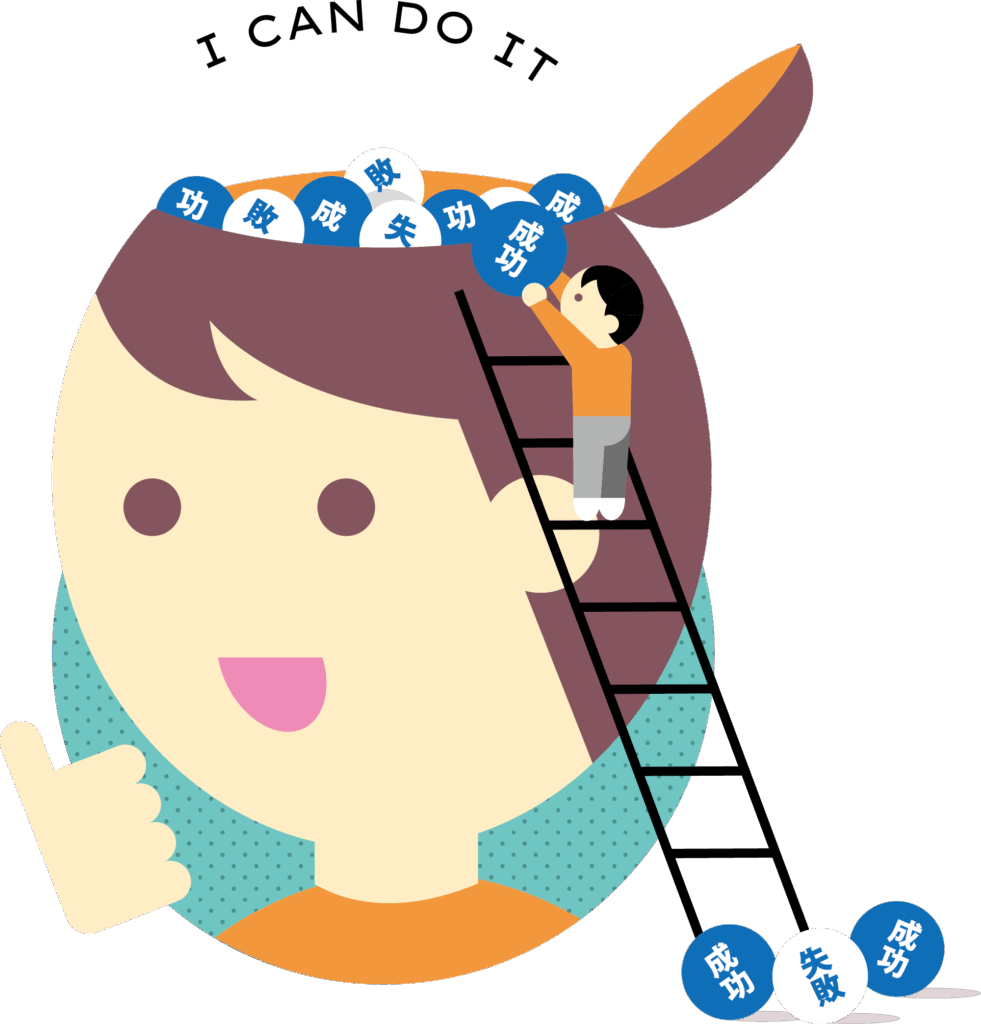
人は信じたい情報を、
つい集めてしまう
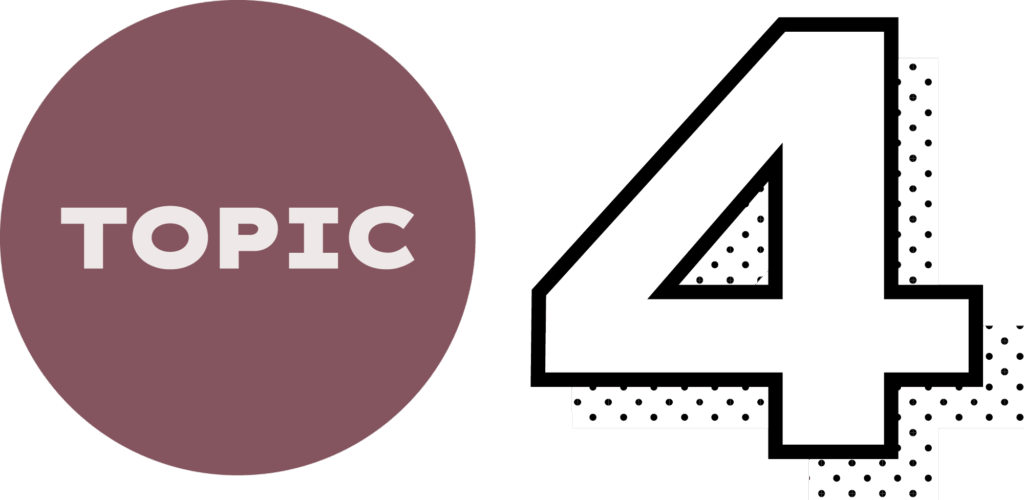
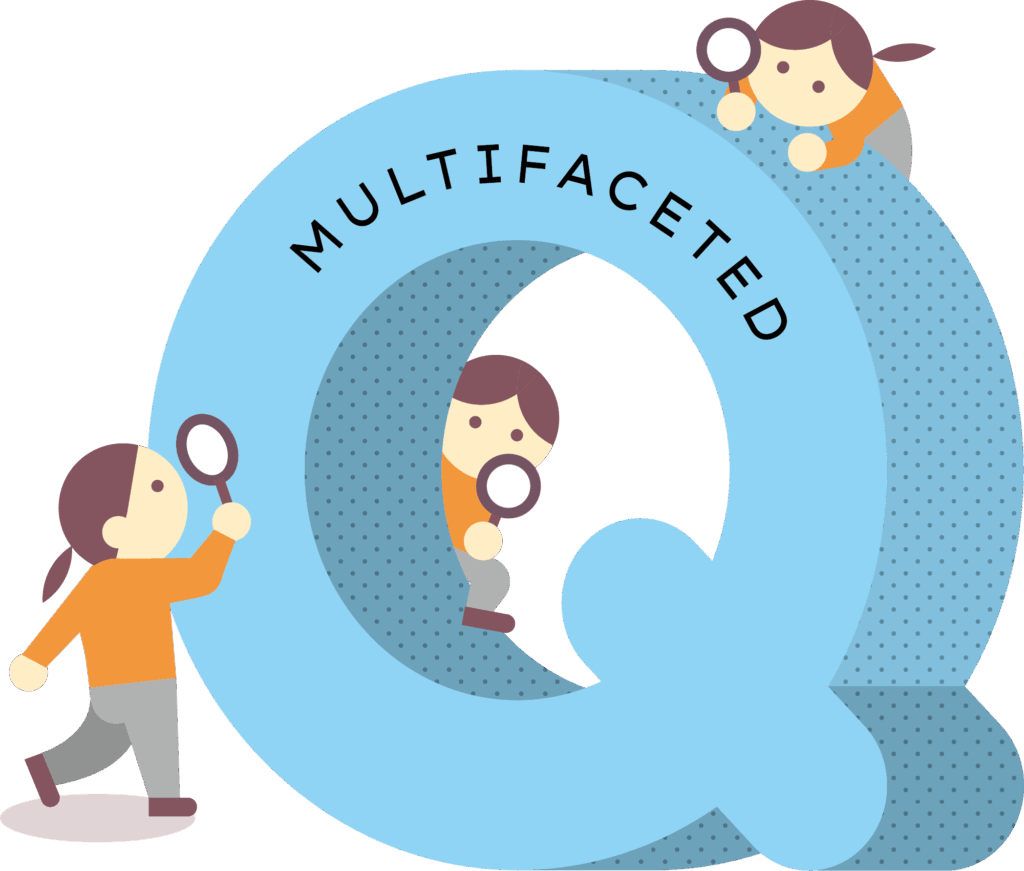
司法犯罪心理学の分野では、「素人理論」という言葉があります。これは専門知識のない人が自身の経験や感覚に基づいて立てた理論のこと。 例えば、ニュースで「家庭環境が犯罪の原因」と報じられると、「やっぱりそうだ」という素人理論ができあがり、ほかの要因は例外として切り捨てられてしまいます。こうした自分の信じる情報ばかりを集めてしまう傾向は「確証バイアス」と呼ばれ、判断の偏りを生む原因にも。私たちは誰しも、自分の感覚や主観を持って生きています。しかし、その「当たり前」を問い直し、専門的な知識から見たときにどのくらい優先されるべきことなのか、直近の状況とどう影響し合うかなど、多面的に見る視点を心理学の学びでは大切にしています。
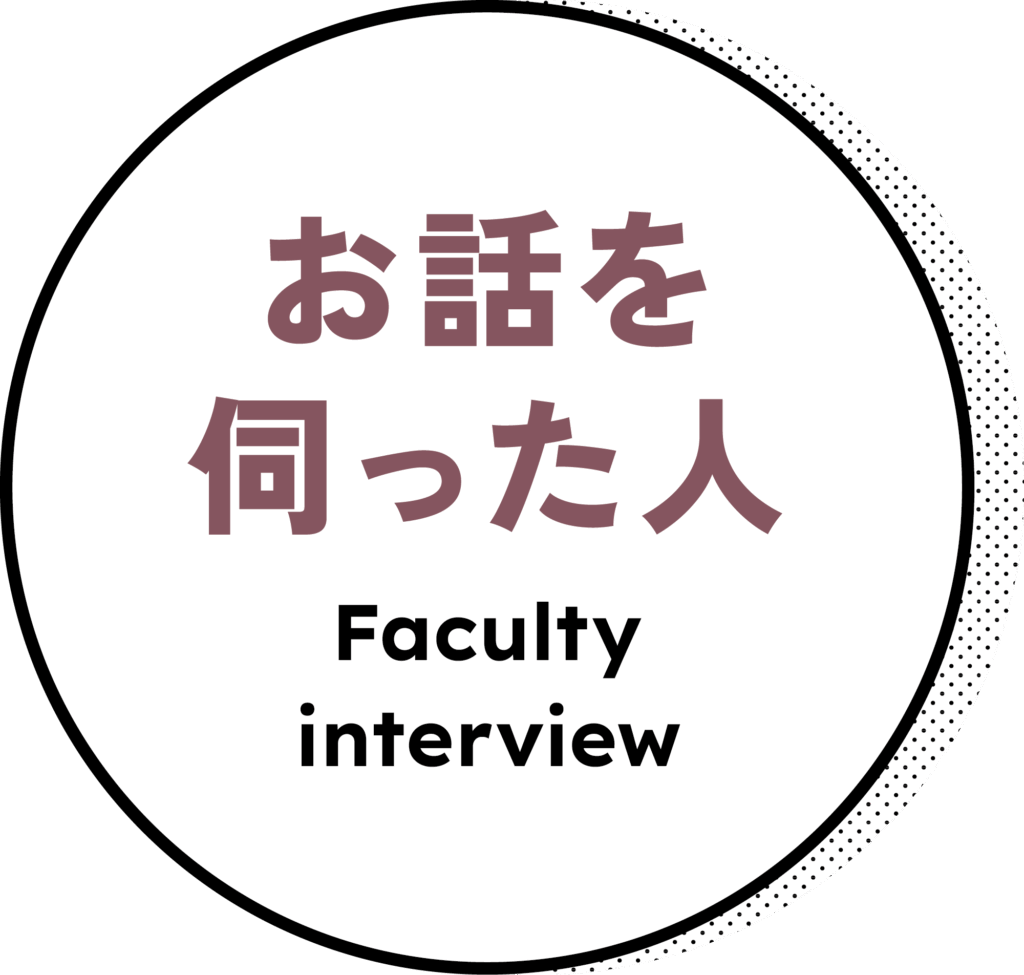

発達心理学では、人が生まれてから一生のあいだに、心や行動がどう変化し、なぜ変化するのかを研究していきます!
人間科学部
人間関係学科 教授
永盛 善博先生
専門分野:発達心理学・教育心理学
担当科目:家族心理学など

心理学は、公認心理師などの専門職にとどまらず、社会のあらゆる場面で役立てることができます!
人間科学部
人間関係学科 講師
内山 博之先生
専門分野:司法犯罪心理学
担当科目:臨床心理学など
- 最新記事
です -
特集
一覧へ戻る -

民俗芸能サークル【舞】
prev≫